グループ活動することあるんだけど、なんかいつも僕しかやってない気がするんだよなあ・・
あんまり手伝ってもらえないしみんな遊んでるし。
いくら言っても聞いてもらえないし、なんかいい方法ないかなあ・・
グループ活動でみんな真面目にやってないのに、自分だけ真面目にやってるのってなんか損している気になっちゃいますよね。
でも、そこでやけになってはいけません。

他の人はともかく、真面目にやっていて損はありません。
私も小学校の時はさぼれない性格というか、周りがやっていなくても一人だけ真面目にしてしまっていたので、何だか損してると言う気がしていました。
でも、今はやっぱりあの時真面目にやっていて良かったなと思っています。
- 周りに流されない意志を強くすることができた
- 先生からの評価が高くなった
- コツコツできる継続力が身についた
とまあ、今はこう思えるのですが当時はそんなこと分かりません。
なので、今小学生で私みたいな性格の子には何かその気持ちを変えられるような本を紹介します。
これを知れば「自分だけが損をしている」という気持ちも変えられて、さらに真面目にやっていない子も活動に引き戻せます。
当時の私が知っていれば、もっと変わったのに!と今更残念がっています

- トム・ソーヤの冒険
- 半日村
- レインボーフラッグ誕生物語
- ピトゥスの動物園
- 楽しいことだと思い、思わせる
- 働く姿をただ見せる
- 信念をつらぬく
- リーダーとしてやるべきこと
楽しいことだと思い、思わせる
トム・ソーヤの冒険
ワンパク少年、トムは悪友のハックと殺人現場を目撃してしまいます。
そして、トムたちは犯人がお金を運びだすのを見てしまい、それを追って洞窟に閉じ込められてしまいます。
なんとか脱出したトムたちはついに宝を見つけ、町の有名人になりますが、トムのいたずらは相変わらずでした。
トムはワンパクで乱暴ですが、頭がよく口も達者な少年です。
『ドラえもん』でいえば、ジャイアンとスネ夫を合わせたような感じですかね。

いたずらの罰として塀にペンキを塗るように言われましたが、そんなこと面倒でとてもやりたくありません。
そこでトムが考えたのは、「誰かにやらせること」でした。
トムがペンキを塗っていると同じ学校の少年たちが次々にトムをからかいながら通り過ぎようとしています。
そこでトムが放った一言は
「好きでペンキ塗ってちゃ悪いのか?ペンキ塗りなんてそうそうやらせてもらえる仕事じゃないだろ?」
この一言でこの少年はペンキ塗りをしたくてたまらなくなり、トムに「俺にやらせてくれよ」とお願いする羽目になりました。
しかし、トムは「これは俺みたいにていねいに塗らないと後で怒られるしな・・・」ともったいつけて少年の興味をさらに引きつけます。
そして、少年は持っていたリンゴを差し出してまで、ペンキ塗りをやらせてもらうことになるのです
同じ要領でトムは「ペンキを塗る権利」を次々に道行く少年たちに売って、その代わりに凧やビー玉、おもちゃなどと交換していき懐を温めていきました。

このことから悪賢いトムは1つのことを学びました。
大人でも子供でも何かを欲しくてたまらない気持ちにさせるには、それを手に入れにくくしてやりさえすればいよい、ということである。
後にトムは自分で学んだこのことを逆に思い知ることになるのですが、それはまた今度ということで。
そこで、トムが学んだことをあなたが生かさない手はありません。
班とかグループ作業で全然協力してくれない子って必ずいますよね。
そしたら、楽しくなくてもとても楽しそうにやってみたらどうでしょうか。
「このプロジェクトに協力しないのは損だ」「これをやるとこんな楽しいことがある」と思わせてみましょう。
その時に「アー楽しいなあ」とかわざと聞こえるくらいの声で楽しさをアピールすると効果的です。
ちなみに、楽しいと思っていると本当に楽しくなってきますよ。
すると興味本位で寄ってきて輪の中に入ろうとしたりするので、その時点では手を出させないようにして無視しましょう。
簡単には仲間に入れてあげないという姿勢を見せることで、ますます相手はやりたくなってきます。
少しじらして気持ちを焦らせ高ぶらせ「早くやらせてくれよ」という気持ちが最高点に達した時点で、「じゃあ、ちょとだけなら・・」とやらせてみてあげてください。
恐らく「やらせてくれてありがとう」と感謝までされるかもしれませんね。
ではそういう人ができることを紹介しましょう!
働く姿をただ見せる
半日村
一平の住んでいる半日村は高い山のせいで半日しか日が当たりません。
そこで、村の少年、一平は「山を削り取る」と袋をかついで山に登りました。
袋に山の土を入れて下りて湖に捨て、また山に登る。
初めは馬鹿にしていた村の子どもも大人も、なんだか協力しないと悪い気がして次々に協力してするようになりました。
それから何年もたち、一平も大人になったころ半日村は一日村と呼ばれるようになりました
[blogcard url=”https://www.meigen-torisetsu.com/hanasakiyama/”]
[blogcard url=”https://www.meigen-torisetsu.com/motimotinoki/”]
大人の世界も子どもの世界も、何か新しいことを始めようとしても周りの人は思ったように協力はしてくれません。
なぜなら、「新しいこと」ととは言いかえれば「誰もやったことのない」ことであり、失敗する可能性が高いからです。

そんな失敗するだろう(頭の固い大人はすぐに決めつけたがりますが)ということに協力しようとする人はまずいないでしょう。
でも、そこであきらめてしまっては言い出しっぺでりーだーであるあなたは「ほら やっぱりね」と鼻で笑われて終わりです。

そこで言葉で協力してもらうように説得するのはあきらめましょう。
その代わりに黙々と一人でもいいので、コツコツ続けましょう。
さっきとちがって楽しい雰囲気がなくても、黙々と一生懸命やっている姿というのは必ず誰かが見ていてくれるものです。
そして、協力しようと思ってくれる人が出てきます。

半日村の一平も「山を削る」と山に登りだしたときは、村人たちに大笑いされました。
みんなは、一平のやろう、ばっかじゃなかろか、気がちがったんじゃなかろかと大わらいした。
ところが、一平が黙々と山と湖を往復していると、なんだか面白そうだぞと真似する子どもたちが出てきました。
そうすると、どんどん真似する子どもたちが増えていって、しまいには大人まであれこれ手を出すようになっていきました。
一平は誰かに協力してくれと頼んだわけでもありません。
ただ黙々と働く姿を見せていただけです。
それでも何年もかかって山が削られて日が差すようになり、一平の目標は達成されました。

中途半端にあきらめずに、コツコツやっていきましょう。
では、実際に会った出来事を紹介しましょう。
信念をつらぬく
レインボーフラッグ誕生物語
レインボーフラッグは、ゲイの人権活動家ハーヴェイ・ミルクとデザイナーのギルバート・ベイカーによって、セクシュアルマイノリティのほこりのシンボルとして生まれました。
色あざやかなレインボーフラッグは、世界じゅうのセクシュアルマイノリティ数百万人の希望とほこりを表すシンボルとなっていきました。

色々な考え方を持ち「たくさんの好き」があるLGBTを表す虹色の旗のことを「レインボーフラッグ」と言います。
この旗を考えたのが、アメリカの議員セクシャルマイノリティのハーヴェイ・ミルクです。
「どんな考えの人も意見を堂々と言え、自分らしく生きられる世の中になってほしい!」と声を上げたのですが、当時はまだそういう考えの人は少なくてどこでも反対ばかりされました。
それでもハーヴェイはあきらめずにアメリカの議員にまでなってセクシャルマイノリティの人たちに対する不公平な法律に講義することを計画しました。
そのためにはたくさんいる反対する人たちに理解してほしいと、見た目に分かりやすいシンボルが必要だと考え、それがレインボーフラッグの誕生につながりました。
ハーヴェイの活動は今まで声を上げられなかったセクシャルマイノリティの人たちを巻き込んで、反対していた人たちの心や考え方をかなり変えることができました。
ハーヴェイはこの活動に反対する人に殺されてしまいましたが、彼の活動はますます大きくなって、今は世界中どこでもレインボーフラッグを目にすることができるようになりました。

さっきと同じことですが、たとえ反対する人がいても協力してくれる人がいなくても、自分の信念を貫いてあきらめずにやってみましょう。
反対する人が多いということは賛成する人も多いということです。
もしかしたら協力したいけど勇気がなくて声を出せない、もしくはまだあなたのやっていることを完全に理解していない のかもしれません。
そういう人たちに分かってもらい声を上げてもらうには、レインボーフラッグのような分かりやすいシンボルがあるといいですね。
特に子供は「仲間だけがもらえるバッジ」なんてあるとワクワクするし仲間意識も強くなりますよね。

リーダーとしてどうすればいいかですね。
それを知るのにピッタリの本があります!
リーダーとしてやるべきこと
ピトゥスの動物園
スペインの6人組の男の子のグループの一人、ピトゥスが重い病気になってしまいました。
彼らはピトゥスの病気を治すお金を集めようと、町に動物園を作って人をたくさん呼ぶことを思いつきました。
ピトゥスのためにお金を集めようと、少年たちはアイデアを出し合います。
まずしたことは、品物を商店街のお店から提供してもらって、福引にして福引券を売る。
そして、チャリティーコンサートを開いて歌手や芸人を無料で呼んでお金を集めました。
今でいうクラウドファンディングですね。

それでもお金は足りないので、彼らは突拍子もないアイデアを思いつきました。
「ぼくたちでつくるんだよ、動物園を!」
まず、少年たちがしたことは、誰か信頼できる大人を味方にすることでした。
そこで、町で信頼のある神父さんに自分たちがどうして動物園を作りたいかをプレゼンして協力してもらえることになりました。
そのついでに動物の知識があった人がいた方がいいだろうと、神父さんは動物学者のプジャーダスさんを紹介してくれました。
そこからはグループのリーダー タネットを中心として活動がどんどん大きくなっていきます。
協力してくれる子どもたちを魅力的な文を書いたチラシで集めます。
集まってくれた子どもたちの特性を聞いた上で、それぞれに合った「動物班」「ポスター班」「会場班」「そうじ班」に分けます。
しかし、「そうじ班」になった子どもたちから不満が出たので、そうじは全員ですることにしました。
それから各班にリーダーを決めて、それぞれ独立して活動を進めていきます。
各班から出たアイデアや活動状況はリーダーのタネットに上げられて、彼がそれをまとめていきます。
活動はどんどん大きくなっていき色んな人を巻き込んでいくのですが、どうなったかはぜひ本を読んで確かめてください。
もし、人がたくさんいるグループのリーダーになったのなら、みんなに楽しく気持ちよく働いてもらうことを考えてみてください。
そのためにはよく観察すること。
- 誰か不満を持っている人はいないか。
- やる気がなさそうな人はいないか。
リーダー一人でできることなんて何もありません。
みんなが動いてくれるからリーダーとしていれるんです。
ここに出てくる少年たちはそれぞれのグループのメンバーの様子をよく観察していて、不満がないようにそれでいて仕事が遅れないようにうまく役割を果たしていました。
あなたもぜひみんなと協力していい活動をしてくださいね。

今日のおさらい♪
- 楽しいことだと思い、思わせる
- 働く姿をただ見せる
- 信念をつらぬく
- リーダーとしてやるべきこと
- トム・ソーヤの冒険
- 半日村
- レインボーフラッグ誕生物語
- ピトゥスの動物園
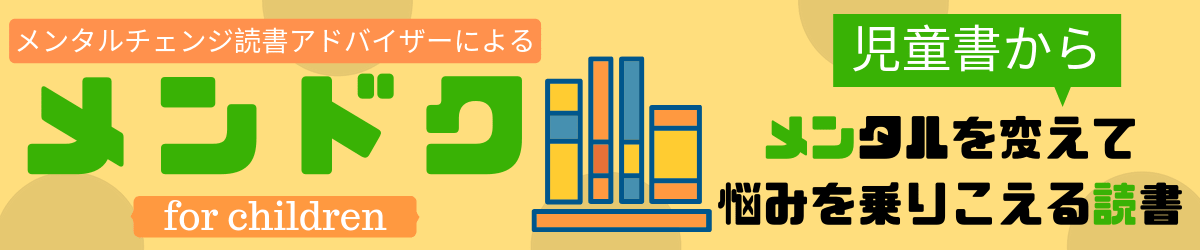




















[…] グループなのに自分だけ真面目にやっていて、周りは全然やってない。そんな時どうしますか? グループ活動でみんな真面目にやってないのに、自分だけ真面目にやってるのってなんか […]